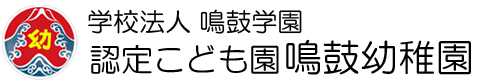折々に思うこと その35
みなさん、短い秋を楽しんでいらっしゃいますか。
今回は、最近の新聞記事の中から、あるコラムを紹介します。題名は「落としどころを探る」というもので、医師で登山家の 今井 通子(みちこ) さんという方が書かれたものです。なぜこのコラムを紹介しようと思ったかというと、集団生活を基本とする幼稚園の生活の中で、トラブルや子ども達の意見がまとまらないような事態が生じた際、「折り合いをつける力」の基礎を培っておくと、その後の集団生活の中で自分を生かしていくことができるからです。以下、今井さんの「落としどころ論」を紹介しましょう。
登山で、自然を相手に「落としどころ」を見つけるのは割と簡単です。自分の体力・気力・技術が見合っているかを確かめればいい。人と人との場合はどうか。私は隊をつくって登ることが多かったのですが、取るべき行動の「落としどころ」は、スキルが最も低い人に合わせるということでした。
高いレベルに合わせると、みな必死になってしまい、意外性のあるアイディアが生まれにくい。低いレベルに設定すると余力が生まれ、可能性が広がります。
日頃のコミュニケーションも大切です。チョモランマ(エベレスト)に挑んだときのこと。頂上にアタックする2人に対して、隊長の私はキャンプ地から強風による中止を訴えました。ところが、うち1人が「僕だけは行くぞ」と。彼はいつも冗談を言う人だったので、みんなは「なら、行ってみろよ」とからかいました。そんな雰囲気も手伝って、彼は私の判断に従ってくれました。
最近はビジネスを含めて決断のスピードが求められる場面も多いでしょう。でも、多数決に頼りすぎ、根気よく「落としどころ」を探ることを放棄してはいないか、「多様性」が大事と言いながら、少数派の意見を切り捨てていないか。
どうしても急いで決めなくてはいけない場合は、判断が間違っていたと分かったときに備え、取り換えるためのいくつかの案を持っておくことが大切です。時に、「失敗は成功の元」と割り切って考えないと、その時点での最適解に行きつくのは難しい。
最近の若い人は、相手を傷つけないように、また自分が傷つかないように言葉を選び、ものをはっきり言わない傾向があると聞きます。互いの意見が平行線であっても、同じ方向を向いていれば出口は見えてきます。そのとき大事なのは、相手を追い詰めない、ひとりぼっちにさせないことです。
人にはその人なりの「正論」があり、それは性格や生き様をも映していることを知る。その上で「それはそうだな、そうかもしれないな」と思えることがあるか。スマホで好きな情報ばかりを読み、自分は正しいと錯覚してしまうと、他者と折り合いをつけ、「落としどころ」を見つけるのはますます難しいかもしれませんね。(朝日新聞 「オピニオン欄」からの抜粋)
いかがでしょうか。なかなか意見が一致しないときに、「折り合いをつけ」、「落としどころ」を見つけるには、まず、相手の言い分をよく聞く。併せて自分の考えや思いもしっかり伝え、いわゆる妥協点がどこかに見つからないか双方で努力する。
このように「聞く力」と「伝える力」が融合した「対話の力」を年少さん(3歳児)の頃から少しずつ培っておくことが大切だと思います。対話が続く(深まる)と、自ずと相手を尊重するようになり、「考える力」も鍛えられていきます。
その土台となるのは、普段からコミュニケーションが円滑に保てる居心地のよいクラスをつくっておくことでしょう。これはクラス担任の経営力にかかっています。4月の初め、担任は『何でも気軽に話せる風通しのよいクラスをつくりたい』と所信表明しますが、クラス経営の最も肝要なところかと思います。それぞれの家庭でも通じるところはありませんか。今日はこのあたりで失礼します。