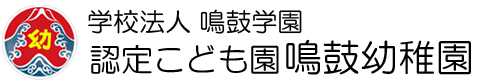折々に思うこと その36(R7.12月)
本園では、午前9時半から午後2時過ぎまでが園児の活動時間です。活動の最後に絵本の読み聞かせの時間を設定しています。この時間、園内では読み聞かせをする各クラス担任の声が静かに流れます。園児達は椅子に座って担任が掲げる絵本を見ながら、朗読に聞き入ります。読み進めるにつれ、園児一人一人の想像の世界が広がっていきます。一日の活動の最後に、このような静寂なひとときを設けることは、教育的にたいへん価値があると思います。どうか、この読み聞かせを通して、本好きで、想像力豊かな子どもがたくさん育ってほしいと思います。心が落ち着くと、預かり以外の子ども達はお迎えの保護者さんと一緒に、また園バスに乗ってそれぞれお家に帰っていきます。
私事で恐縮ですが、読書は嫌いではありません。いつも、どこかに読書の時間をつくろうと工夫しています。まとまった読書の時間を、1日の生活の中に設定することはなかなか難しいので、ちょっとした空き時間を見つけて、その時間で集中して読むというのが私の読書スタイルです。例えば、バスの待ち時間10分、会議が始まるまでの15分、病院で診察が始まるまでの20分、お風呂から上がって寝るまでの30分などなど。「すき間狙い読書」とでも名付けましょうか。そのために携帯バッグの中には、いつも文庫本を1冊しのばせていますし、居間のテーブルの上には、読もうと思う本が常時2~3冊載っています。
そのような私ですが、宵のうちから読み始め、時を忘れて読みはまり、読み終えたときには夜が白々と明けていた、という経験が一度だけあります。はまり込んだその本は、吉村 昭著の「長英逃亡」という本です。『長英』とは、江戸時代末期、当代一の蘭学者と言われた『高野 長英』のことです。その長英が逃亡したという内容の本です。日本国中を、逃げて、逃げて、逃げまくった(約6年と4か月)という逃亡記です。なぜ逃げたのか。当時「蛮社の獄(洋風かぶれを一網打尽にしろ!)」といって、蘭学者が徹底的に弾圧された時期がありました。洋風嫌いの時の奉行が、蘭学を修めた蘭医や蘭学者を手当たり次第に捕らえ、入牢させたり、首を刎ねたりしました。長英も奉行所から目を付けられ、捕まり、小伝馬町の牢に押し込められる(終身禁固刑)のですが、彼は牢内で囚人たちからその高潔な人格を認められ牢名主にまでなります(在牢5年)。やがて彼は牢番を買収し、ある夜、牢に火をつけさせ、そのどさくさに紛れて脱獄したのです。放火・脱獄は前代未聞の大罪です。奉行所の探索方は幕府の威信をかけて執拗に彼を追い続けます。その執念は読んでいて寒気がするほどです。擁護者を求めて日本中を逃走するのですが、安心と思えた場所も、やがて必ず捕吏に嗅ぎつけられます。間一髪の連続。実にスリリングです。手に汗握る思いで読み進めました。逃げ回る中で、長らく会っていない母親に一目会いたいと、彼は陸奥(岩手)の水沢という寒村に赴きます。雪の中、年老いた母とほんのわずかな時間の再会を果たし、後ろ髪を引かれる思いで当地を去っていくシーンは、涙なしでは読めません。
江戸を脱出して、上州(群馬)、米沢(山形)、水沢、越後(新潟)、伊予宇和島(愛媛)と逃走を続ける中で疲れ果てた長英は、逆転の発想で、いっそおひざ元の江戸に潜り込んだ方が安全かもしれないと考え、江戸に潜入。名前を変え、薬品で顔を焼き、町医者としてひっそりと生きていこうとしますが、そこも捕吏に踏み込まれ、ついに捕らえられ、命を奪われてしまうという筋立てです。緊迫した場面の連続で一気に読み終えてしまいました。やや長めの作品ですが、みなさん、よかったらご一読されてみませんか。
僭越ながら、私の心に残る一冊の本の紹介でした。みなさんの心に残っている一冊は何でしょう。今日はこのあたりで失礼します。